夢枕獏・谷口ジロー『神々の山嶺』:「登山家」について
- krmyhi
- 2016年9月10日
- 読了時間: 6分

8月になれば、ガッツリ書けると思っていましたが、なかなか日々の雑務に忙殺されて・・・。
しかし、コツコツ積み上げていくしかないですね。
さて、今年3月に映画化されたこの作品を漫画で読みました。
山ヤの性(さが)にとことん向き合って書かれた、骨太な作品。
物語は、深町という登山隊のカメラマンと孤高の登山家・羽生があるカメラをきっかけにして出会う場面から始まる。深町はそのカメラの行方を追っていくうちに、いつしか羽生という男の存在に魅せられていく。なぜなら、羽生という男は、はるか昔に日本の登山界に大きな旋風を巻き起こしながら、その後行方知らずとなっていた男だったからだ。しかし、その山ヤの権化は、決して偉大な野心を捨てたわけではなく、虎視眈々と自分の野望を実現する機会をうかがっていたのだった。
この作品ではフィルム式カメラがキーアイテムとなっていて、その性格をうまく利用したストーリー構成となっている。ぜひその点も注目してほしい。
今回の本題は、「登山家の是非を問う」。
我ながら、大風呂敷を広げましたね〜笑。
これについて述べるのに、良いシェルパ役を買ってくれるのが「シェルパ」である。
シェルパといえば、この物語でも大きな役割を果たしているが、登山の際に荷物運びやガイド役を行ってくれる人のことを指す。しかし、元々の語源は、ネパールの少数民族だ。彼らがヒマラヤに登る人たちの助役を始めたことが徐々に広まっていき、ヒマラヤ以外の山でもポーターやガイドを行う人のことをシェルパと呼ぶようになった。
現在では少数民族の名称というよりも、職業としての意味の方が定着しているように思う。(さらに今日では、主要国首脳会議(サミット)に先駆けて、調整や予備会議を行う人々もシェルパと呼ばれるようになっている。)
チベット仏教を信奉するシェルパ族にとって、エベレストは信仰の対象であり、登るものではなかったようだ。それが、20世紀以降、海外からのヒマラヤ登山家から外貨を獲得するため、ポーター及びガイドとしての活動をはじめる。この作品は、自分の命を投げ打ってまでもエベレストに固執する登山家の姿を崇高に描いているが、シェルパ族にとって、海外から来る登山家たちは、自分たちの宗教を汚し、文化を破壊するものであった。
また、それと同時に、富を与えてくれるものでもあった点が、難しい部分でもあるのだが。 これを登山家の文化破壊と見なすか、シェルバ族の世俗主義化と見なすかは置いておいて、とにかく、このような文化・信仰的犠牲の上に登山家という存在が成り立っている。それはエベレストに限定されず、世界中の多くの山がー特にその山が高ければ高いほどその確率は高くなるのだがー地域の人々から信仰の対象とされている。数年前に世界遺産に登録された富士山もそうである。富士山は自然遺産として登録されたのではなく、文化遺産として登録されたのである。
また、登山家のもっと重い罪は、山の自然を破壊する点にある。先ほど、文化破壊と述べたが、少数の人が、自然を壊さないように登るのであれば、よほど厳格な山岳信仰のある地域を除き、文化破壊とまでは言えないだろう。しかし、登山家というのは山の自然環境を大きく損なう活動を行う。この作品でも触れられているとおり、エベレスト級の登山となると、一流のプロであっても装備をどんどん山に捨てながら登頂を目指すことになる。さらに昔は今よりも環境保全対策などを講じていなかったため、植生に与える影響は計り知れない。(登山靴についていた一粒の外来種の種が、在来の植生を全滅させることだってありうる。)いわんや、二流のプロ、果てはアマチュアをや、というやつである。
登山がレジャー化した現在となっては、さらに環境に与える影響は大きく、富士山も登山道の汚さから、いつ登録抹消されるかわからない状態である。(アルピニストの野口健さんはこの作品をどう読むだろうか。彼は、エベレストに日本隊が投棄したゴミを見て衝撃を受け、現在では環境活動に積極的に取り組んでいる。山を汚してきたのは登山家であるが、山をきれいにするのも登山家しかいないのだろうか。)
いくら登山自体を認めている山岳信仰であっても、山の植生を破壊されたり、ゴミを投棄されたりしたら、自分たちの文化を汚されたと考えるだろう。 つまり、これまでの登山家の歴史というのは、「人類の限界に挑戦したい」というフロンティア精神が、それぞれの土地のローカルな山岳信仰を飲み込んできた歴史と言える。
フロンティア精神といえば、真っ先に思い浮かぶのは、コロンブスのアメリカ大陸発見だろう。大航海時代以来、西洋の人々は世界中に冒険へと乗り出し、先住民を蹂躙・あるいは懐柔してきた。このような言い方が悪ければ、先住民は来訪者を尊重し、彼らに新しい文化を求めた、といい直そう。
「フロンティア精神は輝かしいものである」というのが、西洋を覆う一つの支配的イデオロギーだったのだろう。
大航海時代の冒険家と20世紀の登山家が同じだと言わないまでも、「フロンティア精神」なるものに価値を見出していなければ、そもそも世界一高い山に登ろうなどと考えないだろう。人類の限界に挑戦しようなどと思わないだろう。「フロンティア精神」とはそういうものなのだ。
そして、現在もそのような価値観はもちろん残っている。
奇しくも、『神々の山嶺』が映画化された今年、『外道クライマー』という本が話題になった。熊野の那智の大滝でロッククライミングを試みたクライマーがその経緯や体験を綴ったものである。これは宗教的に禁止されていたエリアでのクライミングだったため、批判の対象となったが(著者は禁止エリアでの登攀のため逮捕された)これぞまさに、「フロンティア精神VSローカルな山岳信仰」である。
同じく今年7月に、ポケモンGOの配信が始まった。これはさらに身近な問題として多くの人に議論されている。ポケモンGOの問題は、単なる民有地への無断侵入というものも含まれているが、「ポケモンを捕まえたい」という「フロンティア精神」と、「この場所ではゲームをして欲しくない」という寺社や記念公園側の「ローカルな信仰」との摩擦から生じる問題である。
エベレスト登頂には「人類の挑戦」という意義があり、ポケモンには「ただの娯楽性しかない」から両者は区別されるべきだ、というような理由付けは、私は不当だと思う。両者はどちらも、「新しい景色を見たい」「新しいものを手に入れたい」という「フロンティア精神」に則ったものであり、そこに本質的な差異はない。
ただ、一方で、「自然は誰のものでもない」というのも真理かもしれない。「誰のものでもない」ため、登山家が自由に登る権利も否定されない、ということだ。
北欧には、「自然享受権」という考え方が定着している。節度を持って行動すれば、野山のキノコや野生の木の実をその土地の所有者の許可なく採集しても構わないというものだ。きちんと法整備を行い、もちろんガーデニング等で育てているものはダメだが、山や森に行った時などに、万人が自然を楽しむ権利を認めている。
これを拡大解釈していけば、登山家は、山の付近に住む人々の気持ちなど忖度せずに登っても良いことになる。「自然は誰のものでもない」という考え方を前提にすれば、私が述べた「フロンティア精神VSローカルな山岳信仰」という構図自体も成り立たなくなる。
「フロンティア精神VSローカルな山岳信仰」という文化衝突について書こうと思っていたのが、さらに一次元高次の「人間中心主義VS地球環境保全」という問題へ変容してきてしまった。
「登山家の是非を問う」というテーマを立てた場合、どうやら文化衝突だけの論点でなく、人間中心主義批判と絡めて述べていかなくてはならない気がしてきた。
どうやら広げた風呂敷が大きすぎたようである。
今回はこのへんで筆を置きたい。


















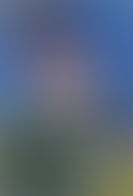

Comments