「三宅一生の仕事」:ファッションと地方都市
- krmyhi
- 2016年5月30日
- 読了時間: 7分

国立新美術館で行っていた三宅一生の仕事展に行ってきた。国立新美術館は、すでに何回か行ったことがあったが、黒川紀章の設計らしい。そうやって見ると確かに中銀カプセルタワーと通底する感覚(センス)のようなものが感じられる。
ちなみに、ウィキペディアで知ったのだが、国立新美術館は英語表記にすると「The National Art Center,Tokyo」。コレクションを持っていないため、「museum」ではなく「Art center」なのだそうだ。へ〜。
さて、まずは余談から。
大学を卒業し、社会人1年目の年、僕はファッションに対する興味がとても薄れてきていたが、その年に亡くなった広告批評家・天野祐吉さんの「外見(そとみ)は一番外側の中身」という言葉で、ファッションに対する興味を持ち直した。身につけるものや髪型、メイクというものは、つまりは自分が他人にどう見られたいかということの表れである、という意味らしい。その後、鷲田清一の著書を読んで、さらに衣服や流行というものへの興味を深めた。
今回の記事も鷲田の著書を所々引用しながら書いていく。
今回の展示は、三宅がいかに素材と構造にこだわった人であるかがよくわかる展示だった。世界をアッと言わせるような「挑戦」に満ちた作品の数々。
例えば、素材で言えば、馬の尻尾の毛などの伝統的なものから未知の新素材まで。
例えば、構造で言えば、蛇腹折りのようにたためる服や、美しい多角形にたたみ込むことができる服。
本当に目からウロコが落ちるような作品ばかりだった。
三宅がその才能を開花させた60〜70年代は、思想と身体所作・身体性をつなぐという考え方が出てきた時代でもあった。以前紹介した土方巽の暗黒舞踏などがまさにそうである。東洋的な身体に宿る、東洋的な所作はとは何か、ということを突き詰めて考え、舞踏という芸術にまで高めたために、土方のパフォーマンスは西洋のダンス界を驚嘆させた。
そのような、身体性と思想の相関性についての再発見がなされている時代に、”誰よりも早くファッションという身体アートに着目し、そこに<自由>に向けて時代をもっとも深く切り裂くことのできる場を見出したのが、三宅一生だった”(p87)のだ。
僕がこの展覧会で感じたのは、三宅の服作りは「衣服を身体に合わせる」➖それは例えばオーダーメードのスーツや身体にぴったりとフィットする肌着 や、「身体を衣服に合わせる」➖それは例えばバストの形を整えるランジェリーやコルセットのような下着 という身体と衣服が主従関係に置かれるようなものではなく、身体と衣服が同等のものとして存在する、もっと言うと身体と素材が共存するような服作りだと感じた。
もしかしたら三宅は「あくまで身体が主役で、衣服は脇役だ」というかもしれない。しかし、彼の素材、構造に対する飽くなき探究心を見ていると、そのような衣服と身体の関係性を目指しているのではないかと感じられたのである。
さて、ここまでが今回の展示の感想。
ここからが本題の地方都市のファッション。
僕は、地方都市の文化の中でも、特にファッション・服飾文化の頽廃はかなり深刻なものだと感じている。以前は商店街に並んでいたセレクトショップが、今はほとんど存在せず、地方の若者がどこで服を買うかといったら、郊外型のショッピングセンターのみである。
もちろん、服に興味がある人は東京まで出て行ってこだわりの一点を求めるかもしれないが、それは本当にごくわずかでしかない。なぜ地方都市のファッション文化はここまで衰退してしまったのか。
地方都市からファッションが失われつつある原因は主に2つあると考える。「場」の喪失と「季節」の喪失である。抽象的に言えば、ファッションと結びついていた「空間」と「時間」の喪失である。空間的にも、時間的にも、メリハリのないのっぺりした状況になってしまったことが、田舎のファッション文化を衰退させた一番の原因だ。
では、一つ目の「場」とは何であろうか。それは、若者が「おしゃれして行こう」と考えるような、「少しだけ特別な場所」「ハレの舞台」のような場所だ。それは別に地方都市に限らず、東京からも失われつつある場所だ。鷲田はそれをファッションのモード(流行)に絡めて以下のように述べている。
”八〇年代のファッション狂想曲のあと、モードなんて知らないよ、というのが、逆におしゃれになった。流行に振りまわされるのがいちばんダサいということになった。ドレスダウンのファッションだ。「ダウン」の緊張感がただの「ダレ」に堕するのは、はやい。都市の表面は、だるくなった。かったるくなってしまった。街に出る悦びが急速にしぼんでいった。気張っておしゃれしてみようかという舞台そのものが、街から喪くなっていった。”(p293)
そうは言っても、やはり東京は特別な場所だ。渋谷、原宿、代官山。おしゃれしていきたい場所はいくらでもある。それに比べて地方の状況は深刻だ。僕の高校時代もそうであったが、友達と遊ぶと言ったら、郊外型のショッピングモールくらいしかないのだ。そりゃ若者のファッションに対する意識も低くなる。
地方には、若者に「おしゃれして行こう」と思わせるような空間が圧倒的に足りないのだ。
次に、二つ目の「季節」の喪失についてである。
先日、オーダーのスーツを作るためにテーラーに寄ったところ、次のような話をされた。
「以前は前橋にも季節があったでしょ。おしゃれなサラリーマンは、ワンシーズンに2、3着はスーツ持ってたからね。でも今はみんなマイカー持ってるから、自宅から職場まで、夏も冬も快適な温度で移動できるでしょう。季節なんか関係ないやね。電車やバスと違って周囲の目もないしね。だからスーツも1年通して2着あれば十分なの。色もオールシーズン使える紺とか黒系しか出ないの。昔はいろんな色が出たよ。春は紺とかオリーブ。夏は薄ねずやブルー系。秋はベージュやブラウン。冬は黒系とかね。みんなマイカーなんて持ってない時代だからね、季節があったけど。今じゃあ・・・。まだ東京の人の方が服に季節感があるよ。あちらは車社会じゃないから」
うーむ。なるほど。確かに、その通りかもしれない。田舎暮らしのお父さんのスタンダード:「自宅と職場を車で行き来するだけの生活」は、全く季節を考慮しなくても良くなってしまう。暑かろうが、寒かろうが、雨が降ろうが風があろうが、車なら関係ない。さらに仕事帰りに遊ぶところもないので直帰すると、赤の他人の視線にさらされることが日常から無くなっていく。これじゃあファッションなんて気にしなくなる。
肌に感じる気温だけではない。
田舎の方が緑が多いから、季節に敏感になれるのでは、と考える人もいるかもしれないが、そんなことはない。確かに遠くに見える山々の色で季節を感じられることは大きいが、車に乗ってしまえば、街路樹や歩道に咲く花などの身近な自然からは遠のく。むしろ自宅から駅まで通勤で歩いたり、手入れの行き届いた公園で週末を過ごしたりする都会人の方が、身近に緑を感じていると言えるかもしれない。
地方における季節感の喪失は、都会のそれよりも深刻なのだ。
若者が集う場を創設することは、現状ではかなり難しい。若者が何を欲しているのかがよくつかめないからだ。とりあえず、僕は地方から失われてしまった季節感を取り戻さなくてはならないと思う。だって、「自然」とか「季節」とかを大切にしなかったら、地方に生きている意味がないでしょう。
季節を感じるには自然と戯れることが一番いい。もちろんバードウォッチングやキャンプ、天体観測などのアクティビティはとてもいいものだ。もっとミクロで話をすると、花や街路樹、昆虫の名前を覚えるだけでも季節に対するセンサーはだいぶ敏感になってくるだろう。しかしながら、今、僕が最も注目しているのは「マルシェ」である。
群馬では、様々な種類のマルシェが開かれている。例えば野菜のマルシェであれば、湖畔や森林公園に小商いをしている農家がいくつか集まり出店し、その土地の、その季節にしか食べられないような野菜を売っている。
僕は知らなかったが、群馬ではこのマルシェ文化が徐々に根付きつつある。4、5月は季節的にもちょうどいいので、毎週末どこかでマルシェが行なわれているという具合だった。マルシェは東京にもあると聞くが、ヒルズマルシェのようなものとは全くの別物だぞ。
(参考)
http://ameblo.jp/organicbus/theme-10065437952.html
https://www.facebook.com/shikishimabooks/
5月の初めに、前橋は敷島公園で行われたブックマルシェに行ってきたが、本当に良かった。
五月の風があり、爽やかな松林があり、心地よい音楽があり、古本や雑貨があり、淹れたてコーヒーの匂いが漂い、子供がいて、女子高生がいて、若い夫婦がいて、三世代の家族がいた。
ヴォネガッド風に言うならば、まさに"If this isn't nice, what is?"というやつだ。
季節を取り戻したいのなら、まずは一年中同じものが並ぶショッピングモールに行くのは避けて、ちょっと不便でもマルシェでお買い物はどうだろうか。
地方の消費動向の今後の変化に期待する。
本文中引用は、
『人はなぜ服を着るのか』鷲田清一


















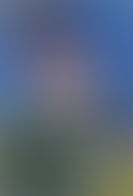

Comments