『赤と黒』:フランスと宗教ー2015年の仏・テロ事件について
- krmyhi
- 2015年12月21日
- 読了時間: 6分
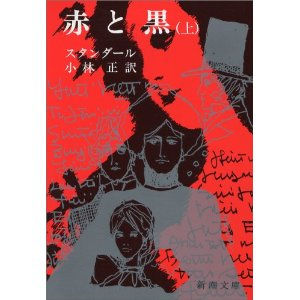
ずっと読もう読もうと思いつつ、読めていなかったスタンダール『赤と黒』をようやく読み終えた。
この作品は、ただのロマンスというだけでなく、当時のフランス社会をよく反映させた作品だとされている。それは、作中に「王党派」「自由主義者」「修道会」といった政治的な単語がたくさん登場することからもわかる。
今回は、前半に『赤と黒』の書かれた時代背景を。後半に現代のフランスと「ライシテ」というイデオロギーについて述べたいと思う。
『赤と黒』は、1814年から1830年までの王政復古という反動の政治社会を時代背景としている。
その王政復古の社会がどのようなものかを確認するために、もう少し時代を遡り、フランス革命から話を始めたい。
17世紀、絶対王政の栄華を極めたフランスは、一部の特権階級にばかり富が集まった結果、第三身分の国民の不満がついに爆発した。それが18世紀末に起きたフランス革命である。国民は自らの手で特権階級を打ち破り、1799年についに皇帝・ナポレオンが誕生し、フランスはナポレオンの時代になる。ナポレオンの時代は、帝政といえど、革命以前の専制君主制とは異なり、共和制的側面を有していた。いわばナポレオンは国民に望まれた皇帝であった。
しかし、1814年にナポレオン帝政が崩れると、事情は一変する。
ルイ18世がフランス国王となり王政をしくと、それに伴い革命を期して国外に亡命していた特権階級(貴族や聖職者)が台頭してくるようになる。
さらにルイ18世の後を継いだシャルル10世は、極端な専制君主を推し進め、急進王党派は一挙に力をつけて政権を握り、イエズス会が強力な勢力でフランスを支配するようになった。
ちなみに、イエズス会とは、ローマ・カトリック教会が母体であり、15世紀以降のプロテスタント拡大に歯止めをかけるために組織された会派である。対するプロテスタントは、汚職などの多かった中世カトリック協会に不満を持ち、聖書の内容に忠実になることを標榜している教派である。
『赤と黒』では、修道会の強権や、上流階級の退屈な社交風俗などがくどい程に繰り返し描かれている。教会の内部や社交界のサロンの描写をたくさん取り入れて、スタンダールはこの時代のフランス社会の息苦しさ、しがらみを表現している。そのような閉塞感は、18世紀の大革命時代から一転、前時代的な一部の上流階級が国民を支配する保守的な王政復古の時代背景から来るものであったのだ。
さて、この『赤と黒』であるが、実は、スタンダールは現実に起きた2つの事件をモデルとして、この物語を作り上げた。
二つの事件はどちらも、青年が起こした、色恋沙汰に端を発した流血事件である。
スタンダールはこの二つの事件を、保守的で凝り固まったフランス社会において、おそるべきエネルギーを発している「情熱の犯罪」だとして、賞賛を送っている。
スタンダールは、フランスの政治情勢についての描写に加え、実際の事件を物語のモチーフすることで、この『赤と黒』を当時のフランス社会についての高い批評性を持った物語にしたのだ。
ちなみに、この『赤と黒』という題名の意味について、訳者・小林正は、以下の説を紹介している。
1.赤はナポレオン時代の栄光を、黒は聖職者の黒衣、すなわち修道会の野望
2.赤はエネルギーの燃える大革命および帝政時代、黒は退嬰的で陰鬱な王政復古の時代。
その他、自由主義者と修道会の対立闘争であるという見方や、神学生が刃傷沙汰で黒衣を血で汚すことの象徴であると見る説
さて、ここから本題。
今年2015年は、フランスで大きなテロ事件が二つも起きた年となった。一つは1月に起きたシャルリエブドの襲撃事件。もう一つは、11月に起きた、パリ同時多発テロ。東京新聞に連載を持っているある社会学者は、今年最初の原稿がフランスのテロ事件で始まり、今年最後の原稿もフランスのテロ事件で締めくくることとなったと述べていた。
なぜ、パリが狙われることになったのか。いろいろなところですでに解説されていることであるが、主に二つの理由が挙げられる。
一つは、パリが世界有数の大都市であるため。
例えば、シリアやイラクで民間人が日に何十人と殺されても、先進国は興味を示さない。世界が誇る「花の都」であるパリでテロを行うことで、ISは先進国に住む人々の恐怖を煽ることができる。
そして、もう一つの理由が今回のテーマなのだが、フランスは宗教に不寛容な国であるためにテロリストの標的にされた、という見方がある。多くのテロリストたちは、フランスはイスラーム教に対して不寛容であると主張する。
なぜフランスは「宗教に不寛容」とされるのか。そこには、フランス共和国の精神的支柱である「ライシテ」という理念が隠れている。
「ライシテ」は、「政教分離」や「宗教的中立性」「非宗教性」を意味するイデオロギーである。なぜフランスでは、「ライシテ」というイデオロギーが大切にされてきたのだろうか。
その答えこそ、まさに『赤と黒』で描かれていた、国家と宗教が強固に結びついた時代があったからなのである。
当時、カトリック教会は、国家と強力に結びつき、国民を支配していた。それに嫌気がさし、政治と宗教は切り離すべきだと考えたフランス国民が生み出したのが、「ライシテ」というイデオロギーなのである。以後、フランス国民は、民主主義が強まるにつれて、政教分離を徐々に達成してきたのである。
さらに、時代とともに「ライシテ」が意味するものは変遷してきた。
『赤と黒』で描かれたような社会においては、「ライシテ」の意味するものは、政治と宗教の「分離」であった。しかし、時代が移り現在では、国家が多様な宗教に対して「平等性」を与えること、ひいては公共の場での「宗教色の排除」につながっている。
現代における「ライシテ」の先鋭的な例が、世界的注目を浴びた「スカーフ問題」である。
パリ近郊のある中学校で、イスラム教徒の女子生徒が、スカーフを着用したまま教室に入ることを禁止された。それを皮切りに、公立学校というパブリックな場におけるスカーフの着用について、大々的な議論が巻き起こった。
※ちなみに、カトリック系の私立学校であれば、国が宗教性を排除するようなことはできないため、この議論に含まれることはない。しかしながら、フランスは例によって「ライシテ」の理念により、20世紀初頭にカトリック修道会が経営していた私立学校を1万校以上閉鎖させた。そこに通っていた生徒の多くは、公立学校に吸収されることとなった。
初め国務院*は、スカーフの全面的禁止は難しいと考え、ケースごとに判断すべきだという
立場を取っていたが、国民的議論の高まりによって、法律を解決手段とせざるをえなくなった。そのため、時のシラク大統領は、2004年スカーフ等目立つような宗教的しるしを禁止する法律を国務院に提出した。
現在、様々な方面から批判が上がりながらも、この法律は施行されている次第である。
「スカーフ問題」のような例を見ると、確かにフランスは宗教に不寛容であるようにも思える。(もちろん一概には言えない。例えばこのような法律は日本にはないが、果たして日本の飲食店でハラル食材を扱っている店が一体どれくらいの割合で存在するだろうか)
現在の、宗教的に不寛容なフランスのあり方は、『赤と黒』で描かれたような政治と宗教が結びつき、人々を金銭的にも精神的にも支配していた時代の反動とも言える。
「宗教的中立性」や「政教分離」ということの難しさを改めて感じさせられる1年となった。
*フランス国務院:行政訴訟の最高裁判所しての役割を持つ、政府の諮問機関。ちなみに司法訴訟における最高裁判所は破毀院。
【参考文献】
http://www.totetu.org/assets/media/paper/k020_262.pdf


















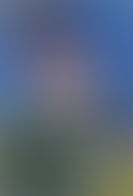

Comments