ジャック・ケルアック『路上』:元祖カウンターカルチャー
- krmyhi
- 2015年6月25日
- 読了時間: 5分
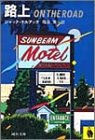
この書は、1950年代にアメリカの若者の間で流行した「ビート」や「ヒーッピー」達のバイブル的な作品です。彼らはビートジェネレーションと呼ばれ、既成の価値観を次々と打ちこわしていきました。そしてその背景には、米兵が大義なく出兵したベトナム戦争が存在します。
少し前にNHKで「日本戦後サブカルチャー史」という番組がやっていました。劇作家の宮沢章夫が、日本の戦後のサブカルチャーについて、独自の解釈で解説を行っていくという番組です。
この番組においても、アメリカ50年代のビートジェネレエーションが出発点となっていました。つまり、今の日本のサブカルチャーの源流にこの『路上』という作品があるということらしいのです。
確かに、この小説には今の日本の若者文化の「祖先」達がたくさん登場します。
たとえば、登場人物は車に乗って猛スピードで大陸を横断しますが、これは日本の「暴走族」のはしりかもしれません。モダン・ジャズのナイトクラブはダンス・クラブ、マリファナはドラッグと、今日の日本にも脈々と続く「カルチャー」のるつぼです。
カウンターカルチャーとサブカルチャーについて、きちんとした定義付けはありません。ただ僕の理解では、ドラッグや暴走など反道徳的なものや暴力的なものは「カウンターカルチャー」、歴史の浅さなどの理由から文化の中心は担えないものを「サブカルチャー」に分類しています。もちろん、「カウンターカルチャー」と「サブカルチャー」に明確な線引きはできませんし、「メインカルチャー」とそれらの間にも明確なボーダーはありません。
ただ、「マンガ」や「原宿ファッション」などはこれから先もずっと「サブカル」と呼ばれるような気がします。クラシック(古典)が単に作られた年代を表わす概念ではなく一つのジャンルとして扱われているように、「サブカル」という言葉も市民権を得るのと共に、「メインカルチャー」との相関から使用されるのではなくなってきたような気がします。今まではあくまで「メインカルチャーの下(サブ)にあるもの」ということで、「サブカルチャー」は絶えずその立ち位置を探っていましたが、昨今はイメージが固定化し、単にマンガやアニメ、アイドル、ゲーム等を指すようになっているようです。
『路上』に登場するような「カウンターカルチャー」を生み出す精神文化こそが、アメリカの最大の武器だと述べる明晰な洞察者が、日本にいます。そう、内田樹です。←またかよ笑
ちょっと長いですが、その部分を引いてみます。
占領時代にアメリカは、日本国民に対してきわめて効果的な情報宣伝工作を展開し、みごとに日本の言論をコントロールしました。しかし、親米気運が醸成されたのは、単なる検閲や情報工作の成果とは言い切れないと思います。アメリカ文化の中には、そのハードな政治的スタイルとは別にある種の「風通しのよさ」があります。それに日本人は惹きつけられたのだと思います。 戦後まず日本に入ってきたのはハリウッド映画であり、ジャズであり、ロックンロールであり、レイバンやジッポやキャデラックでしたけれど、これはまったく政治イデオロギーとは関係がない生活文化です。その魅力は日本人の身体にも感性にも直接触れました。そういうアメリカの生活文化への「あこがれ」は政治的に操作されたものではなく、自発的なものだったと思います。 同じことは1970年代にも起こりました。大義なきベトナム戦争によって、アメリカの国際社会における評価は最低レベルにまで低下していました。日本でもベトナム反戦闘争によって反米気運は亢進していた。けれども、70年代はじめには反米気運は潮を引くように消滅しました。それをもたらしたのはアメリカ国内における「カウンター・カルチャー」の力だったと思います。 アメリカの若者たちはヒッピー・ムーブメントや「ラブ・アンド・ピース」といった反権力的価値を掲げて、政府の政策にはっきりと異を唱えました。アメリカの若者たちのこの「反権力の戦い」は映画や音楽やファッションを通じて世界中に広まりました。そして、結果的に世界各地の反米の戦いの戦闘性は、アメリカの若者たちの発信するアメリカの「カウンター・カルチャー」の波によっていくぶんかは緩和されてしまったと思います。というのは、そのときに世界の人々は「アメリカほど反権力的な文化が受容され、国民的支持を得ている国はない」という認識を抱くようになったからです。「ソ連に比べたらずっとましだ」という評価を無言のうちに誰しもが抱いた。ですから東西冷戦が最終的にアメリカの勝利で終わったのは、科学力や軍事力や外交力の差ではなく、「アメリカにはカウンター・カルチャーが棲息できるが、ソ連にはできない」という文化的許容度の差ゆえだったと思います。 統治者の不道徳や無能を告発するメッセージを「文化商品」として絶えず生産し、自由に流通させ、娯楽として消費できるような社会は今のところ世界広しといえどもアメリカしかありません。 アメリカが世界各地であれほどひどいことをしていたにもかかわらず、反米感情が臨界点に達することを防いでいるのは、ハリウッドが大統領やCIA長官を「悪役」にした映画を大量生産しているからだと私は思っています。アメリカの反権力文化ほど自国の統治者に対して辛辣なものは他国にありません。右手がした悪事を左手が告発するというこのアメリカの「一人芝居的復元力」は世界に類を見ないものです。 アメリカの国力の本質はここにあると私は思っています。 これはアメリカ政府が意図的・政策的に実施している「文化政策」ではありません。国民全体が無意識的にコミットしている壮大な「文化戦略」なのだと思います。
(内田樹の研究室『対米従属を通じて、「戦争ができる国」へ』http://blog.tatsuru.com/2015/06/22_1436.php)
ぼくは初めて「シンプソンズ」の設定を知った時に、度肝を抜かれた。シンプソンズの主人公ホーマーは、原子力発電所の職員だが、時々いい加減な仕事をして原発を爆発させてしまったりしている。あんな間抜け顔が主人公のバカアニメで、あそこまでぶっ飛んだことができるアメリカの「底の深さ」にぼくは驚愕した。日本だったら、絶対に「不謹慎」という言葉によって駆逐されてしまっただろう。
良くも悪くも日本には「不謹慎」という言葉があり、アメリカにはない。(多分)
なるほど、「カウンターカルチャー」の定義に、一つ要件が加わった。
「不謹慎」という言葉が当てはまるかどうかだ。「サブカルチャー」は「不謹慎」には当たらないだろう。




















Comments