安部公房『内なる辺境』:「正統な国民」
- krmyhi
- 2015年6月21日
- 読了時間: 6分
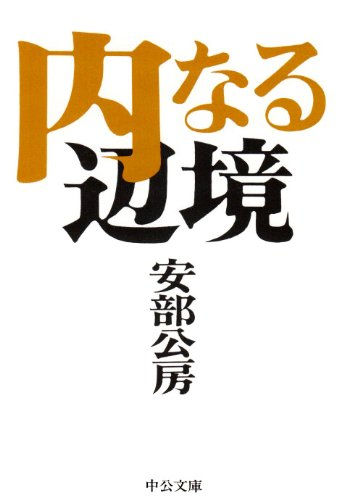
やはり安部公房の文章は面白い。一つの事柄・思想・理論について、色んな角度から眺め、つつき回し、戯れる。そしてその戯れ方は実に論理性に富み、合理的である。安部公房は東大医学部を卒業しているが、かなり数学ができたのではないかと文章を読む度に思ってしまう。
『内なる辺境』は小説ではなくエッセイ3本がまとめられた作品だが、どれも「正統」と「異端」というものを主題にして書かれている。
その中でも、表題作「内なる辺境」というエッセイは、ユダヤ問題に軸に、なぜユダヤ民族が「異端」と呼ばれるかに言及しながら、現代人の誰もが心の中に持つ「内なる辺境」について述べている。
ぼくが最も衝撃を受けたのは、ヒットラーがドイツ農民を「正統な国民」とし、ユダヤ人は都市的であり、反自然的であり、人工的であるために排斥の対象となったという事実である。
ナチスが国家の正統を、農民に定めていたとは知らなかった。そしてどうやら、それはナチスだけに限らなかったようである。ここで公房のユダヤ人についての記述を引いてみる。
ユダヤ人の都市的性格は、排外主義的なデマゴーグの手による悪意に満ちた手配写真であると同時に、歴史的な裏付けをもった事実であった。いかに寛大な国王や領主でも、永遠の他国者であるユダヤ人が、その聖なる農村地帯に足を踏み入れることだけは絶対に許せなかった。ただ都市にだけ居住権を認め(ゲットー)、キリスト教徒にとっては不浄の行為とみなされていた金融業—不浄ではあっても、すでに国家経済の中で不可欠の要素になっていた—に従事させたりすることで、けっこう持ちつ持たれつの関係を維持させていたのである。
なるほど、公房の論によると、昔は共同体の構成員の「正統」を農民に求めた領主が多かったらしい。確かに、ユダヤ人の歴史的性格と照らし合わせても、最もらしいことが分かる。
では、なぜ公房の論がぼくに衝撃を与えたかに戻る。
農民を国民の「正統」に置く、という思想は、内田樹が現代日本の政治に求めるものと相似的な部分がないだろうか。内田は彼のポリシーについて、自身のブログで以下のように述べている。
国民経済というのは、日本列島から出られない、日本語しか話せない、日本固有のローカルな文化の中でしか生きている気がしない圧倒的マジョリティを「どうやって食わせるか」というリアルな課題に愚直に答えることである。(内田樹の研究室「百年目のトリクルダウン」http://blog.tatsuru.com/2011/11/25_1036.php)
ここでは、内田は雇用について語っているため、「国民経済」が主語となっているが、これを「国の政策」に置き換えて読んで欲しい。基本的に内田の主張は、国の制度設計をするときは、—それは福祉であっても教育であっても—いわゆる「グローバル人材」のような「世界中どこでも働き、生きていける人」ではなく、「日本でしか生きることができない人」に主眼を置くべきだ、というものである。そのため、この文章の「国民経済」を「国の政策」と置き換えても、内田先生に怒られることはないだろう。
ぼくは現代日本の政治は、「都市部に住むサラリーマン」を基準に制度設計を行なっているように感じている。そしてそれはある種「弱者切り捨て」だと思っている。なぜなら、ぼくが漠然とイメージする「都市部に住むサラリーマン」は土地に縛られていないからだ。いや、もちろんよく考えてみると、サラリーマンだって土地に縛られて生きている。もし明日、東京大震災が起こりビルというビルがすべて倒壊してしまったら、サラリーマンの多くが失業に追い込まれることだろう。他の都市や国に支社や出先機関がある大企業に勤めている人間よりも、そんなものを持たない中小企業で働く人間の方が多いはずだ。
しかし、第一次産業に従事する人達の被害は彼らの比ではないだろう。農業でも漁業でも、その土地・その海を守り、共に生きていくことがすべてである。商売は土地を変えてもできるかもしれないが、農家にとって所有する土地というのは代替不可能なのである。
もちろん、現在の日本の人口比率からすると、第一次産業に従事する人よりも第二次・第三次産業に従事する人の数の方が多いため、「都市部に住むサラリーマン」に主眼を置くことは間違っていないのかもしれないが、第一次産業は国の生命線であることを忘れてはいけないとぼくは思う。
そのため、内田樹の言葉に深い感銘を覚えたのだ。それまで、そのようなことを言う人を他に知らなかったため、斬新ささえ感じていた。
しかし、この「日本列島から出られない、日本語しか話せない、日本固有のローカルな文化の中でしか生きている気がしない圧倒的マジョリティ」に主眼をおいて政策を練るということと、ヒットラーの農民を国民の「正統」と位置づけることが、構図的にこんなにも相似であるなんて。
もちろん、構図が似ているというだけで、内田は「グローバル人材」を排斥しろなどという乱暴なことは言っていない。ただ、今までぼくが支持していた内田の主張にも、弱点があるということがわかったのだ。そしてその弱点は、世界地図に線引きをしてすべての地域を「農耕型」(つまり定住型)社会にしてしまったグローバル資本主義というものに、疑問を呈しているぼくにとってはアキレス腱ともなりえるものなのだ。
『内なる辺境』を読んで、もしかしたら今日の先進国は、農耕型の社会からユダヤ人型の社会への変革を遂げようとしているのかもしれない、と感じた。今まで先進諸国は、世界中に線引きを行なうことに躍起になっていた。それは、人々の定住を基礎とした農耕型社会を世界のスタンダードにするという動きだった。
しかし今、地図上に線引きすることを終えた先進諸国(の支配層)は、後進国あるいは自国の被支配層を特定の土地に縛り付けたまま、自分たちだけは自由に移動して生活できるような世界に変えようとしているようだ。
もしかしたら、先進国はイスラーム世界やユダヤ人に嫉妬していたのかもしれない。土地という概念に縛られず、あらゆるボーダーを飛び越えて生きる彼らに。
PS
その後、公房の論はユダヤ人とは一体何者か、という問いかけに対して次のように答えている。
ともかく、反ユダヤ主義なるものの根拠が、ユダヤ人の存在そのものよりも、むしろ「本物の国民」という正統概念の要請の内部にひそむ、一種の自家中毒的症状だと考えて、まず間違いはなさそうだ。ユダヤ人の存在が、反ユダヤ主義を生んだのではなく、正統概念の輪郭をより明瞭に浮かび上がらせるための、意識的な人工照明として、ユダヤという異端概念が持ち出されてきたらしいのだ。ユダヤ人は存在していたのではなく、存在させられていたのである。この原因と結果の倒錯の責任が、異端の異端性にではなく、もっぱら正統の正当性に帰せられるべきものであることは、いまさら疑う余地のないことだろう。
異端の異端であるべきゆえんを、正統の側から背理法的に導き出す公房の明晰な洞察に、ただただうっとりとしてしまう。




















Comments